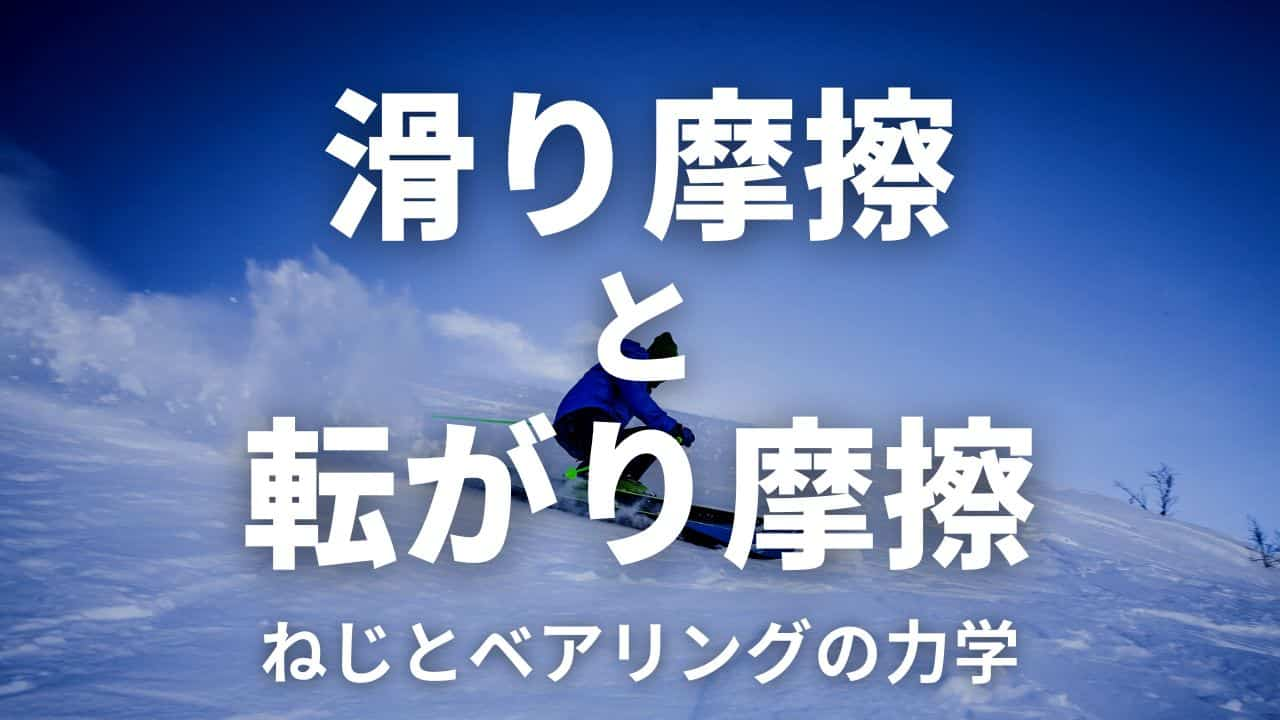圧力とは、垂直方向から働く力の単位面積当たりの大きさのことです。
圧力は単位面積当たりの力であるため、微分や積分の計算との相性が良く、使い勝手の良い物理量でもあります。
今回は圧力の定義や流体から受ける圧力の性質について解説し、浮力が生じる理由を計算により示します。
流体の密度を$\rho$、重力加速度を$g$とすると、体積$V$の物体には、以下で表される大きさ$F$で上向きの浮力が働く。
\begin{split}
F=\rho Vg
\end{split}
なお、浮力の大きさは流体の密度と物体が排除した流体の体積のみで決まり、物体の密度や流体中での深度とは無関係である。
さらに、船の安定性についても議論します。
圧力とは?
圧力は、垂直方向から働く力の単位面積当たりの大きさとして定義される物理量のことです。
例えば、面積$S$の平面に垂直方向に合計の大きさが$F$の力が働くとき、この面に働く圧力$p$は次のように表せます。
\begin{eqnarray}
p = \ff{F}{S} \\
\,
\end{eqnarray}
圧力の定義で重要な点は、垂直方向から働く力について考えていることです。
例えば、図のように斜めの方向から大きさ$F$の力が働いているとき、圧力の計算に含める力は$F$を垂直方向に分解した$F_n$となります。
したがって、$p = \DL{\ff{F_t}{S}}$となります。
このように、大きさ$F_t$の水平方向分力は圧力の計算に含まれません。
圧力と応力
さて、圧力の定義として高校物理の教科書や参考書では、『単位面積当たりに働く力の大きさ』として紹介されますが、この定義は正確には応力と呼ばれる物理量の定義に該当します。
例えば、垂直方向から働く力の単位面積当たりの大きさことを垂直応力と呼びます。垂直応力の中でも、面を押し合う垂直応力のことを圧力と呼ぶのです。
例えば、垂直方向から働く力の単位面積当たりの大きさことは垂直応力と呼びます。垂直応力の中でも、面を押し合う垂直応力のことを圧力と呼ぶのです。
一方、水平方向から働く力の単位面積当たりの大きさは、せん断応力と呼びます。せん断応力を式で表すと、$\DL{\ff{F_t}{S}}$となります。
応力:単位面積当たりに働く力
圧力:面に対して垂直かつ面を押し込む方向に働く単位面積当たりの力
圧力と応力の違いについて神経質に意識する必要はありませんが、材料力学と呼ばれる物体の変形を議論する力学分野では応力という用語が頻繁に登場します。
応力については、【応力とひずみ】現実の物体に働く力と変形はどう表現できるか?にて詳しく解説しています。
パスカルの原理(圧力の等方性)
突然ですが、空気や水のような気体や液体のことを流体と呼びます。(正確には、静止した状態で内部にせん断応力が働かない連続体のことを流体と呼びます。)
特に、静止流体中での圧力の性質について考えましょう。(静止流体とは、文字通り流体中の中で対流などの流れが無い流体のことです。)
静止流体中では対流などが無いため、静止流体中の微小要素に働く力は釣り合っていると言えます。
微小要素として、次のような三角柱を考えます。
なお、ここで考えている微小要素は圧力により体積が変化しないとします。
さて、三角柱の斜面に大きさ$p$の圧力が働いており、図のような垂直な面に$p_x$、水平な面に$p_z$ の圧力が働いているとします。
この微小要素は静止しているため、各面に働く力は釣り合っています。
力が圧力と面積の積であることに注意すると、次のような力の釣り合い式を立てられます。
$$
\left\{
\begin{eqnarray}
p\sin\theta\cdot \diff y\diff s = p_x\cdot \diff y\diff z \EE
p\cos\theta\cdot \diff y\diff s = p_z\cdot \diff x\diff y
\end{eqnarray}
\right.
$$
$\DL{\diff s = \ff{\diff x}{\cos \theta}}$であることを利用すると上式は、
$$
\left\{
\begin{split}
&p\sin\theta\cdot\diff x = p_x\cos\theta \cdot\diff z \EE
&p\cdot\diff x = p_z\cdot \diff x
\end{split}
\right.
$$
と変形できます。
第二式より、$p = p_z$となることが分かります。
さて、第一式について考えましょう。
微小要素の幾何学的関係から、$\DL{\tan\theta=\ff{\diff z}{\diff x}}$であることを考慮すると、第一式は次のように変形できます。
\begin{split}
&p\sin\theta\cdot\diff x = p_x\cos\theta \cdot\diff z \EE
&p\tan\theta = p_x\ff{\diff z}{\diff x} = p_x\tan\theta \EE
\end{split}
これより、$p=p_x$となることが分かります。
以上のことから、$p = p_x = p_z$となることが言えます。
他の面についても同様に計算すると、$p = p_x = p_y = p_z $であることが示せます。
したがって、流体中の微小要素(一点)に作用する圧力の大きさは向きによらず一定であることが示されました。
このことをパスカルの原理または、圧力の等方性と呼びます。
流体中の一点に作用する圧力の大きさは向きによらず一定である
※ ここでは微小要素自体の質量について無視して計算を進めましたが、微小要素の質量を考慮した圧力の計算は後ほど行います。
パスカルの原理の応用
静止流体が水や油のような非圧縮性流体である場合、工学的に有用な応用ができます。
パスカルの原理の工学的な応用について紹介します。
出入口の断面積が$S_1, S_2$($S_1 < S_2$)である容器に流体を満たし、片側に質量$m_1$のおもりを載せます。
このとき、もう片方の出口にどれくらいの大きさの質量を置けば、釣り合いが取れるでしょうか?
まず、断面積$S_1$の板に働く力$F_1$は$m_1g$なので、この板に働く圧力は$p_1 = \DL{\ff{F_1}{S_1}}$となります。
さて、反対側の板に働く圧力を$p_2$とすると、パスカルの原理より$p_2 = p_1$となります。
このことより、板全体に働く力$F_2$は、$F_2 = p_1 S_2$と計算できます。
以上の式を繋げると、
\begin{eqnarray}
F_2 &=& m_2 g \EE
&=& p_1 S_2 \EE
&=& \ff{S_2}{S_1}F_1 \EE
m_2g &=& \ff{S_2}{S_1}m_1g \EE
\therefore \, m_2 &=& \ff{S_2}{S_1}m_1
\end{eqnarray}
とできて、$m_2$が求められます。
計算結果より、小さな質量でも大きな質量を持ち上げられることが分かります。
今回は錘を載せましたが、$S_1$に力を加えても同じ状況を作り出せるため、小さな力でも重い物体を動かせることを意味します。
非圧縮性流体のこのような性質を利用した機械の代表例が油圧シリンダーです。自動車のブレーキやクレーンに組み込まれています。
※ 左右で増減する流体の体積は等しいため、移動距離は$S_2$の方が常に小さくなります。このように移動距離と力の積である仕事について検討すると、左右での仕事は一定になることが分かります。
圧力と深度の関係
浮力の話題に移る前に、流体自身の重みによる圧力変化について考察しましょう。
図のような、断面積が$S$で高さ$h$の仮想的な四角柱を考えます。
この四角柱の上面に$p_0$の圧力が働いているとし、下面には$p_1$の圧力が働いているとします。
この四角柱の質量が無視できるとき、$p_0 = p_1$となることはパスカルの原理より明らかです。
では、四角柱の質量が無視できないとき、下面の圧力がどうなるのかについて考えてみましょう。
流体の密度を$\rho$(ロー)とすると、この四角柱の質量は$\rho Sh$となります。
また、重力加速度を$g$とすると、円柱自体の重さは$\rho Shg$となります。
上下の面で力が釣り合っているため、次のような式が成り立ちます。
\begin{eqnarray}
p_1 S &=& p_0S + \rho Shg \EE
\therefore\, p_1 &=& p_0 + \rho gh \tag{1}
\end{eqnarray}
これより、圧力は深さに比例して増加することが分かります。
浮力の起源
準備が整ったので、浮力についての考察を行いましょう。
密度が$\rho$の流体中に直径$2r$の密度$\rho’$の球体を置き、この球体が周囲の流体から圧力を受けているとします。
このとき、球が流体から受ける正味の力がどうなるのかについて計算しましょう。
いきなり全体の力を計算するのは難しいため、球面上の微小な面積に働く力から考え始めます。
具体的には、$z$軸から$\theta$離れた位置にある、面積が$r\diff \theta\cdot r\sin\theta\diff \varphi\,\, (= r^2\sin\theta \diff \theta\diff \varphi) $の微小要素に働く力$\diff f$について考えます。
このように物理学の問題に取り組む典型的な戦略として、微小な要素から考え始め、これらを足し合わせることで、全体の状態を求める手法を取ります。
パスカルの原理より、この微小要素に対して法線方向(面に対して垂直方向)から大きさ$p$の圧力が働くことが言えます。
原点の位置に働く圧力を$p_0$とすると、今考えている位置に働く圧力$p$は、式(1)より、
\begin{eqnarray}
p = p_0 \,- \rho g r\cos\theta
\end{eqnarray}
と表せます。
微小要素に働く圧力が一定であると近似できるため、微小要素に働く力の大きさは、上式も利用して、
\begin{eqnarray}
\diff f &=& p\cdot r^2\sin\theta \,\diff \theta\diff \varphi \EE
&=& (p_0r^2 \,- \rho g r^3\cos\theta)\sin\theta\,\diff \theta\diff \varphi
\end{eqnarray}
と表せます。
今回は、微小要素を$z$軸周りに一回転させたリングを計算し、さらにこのリングを$\theta$について$0$から$\pi$まで動かすことで、球の表面に働く力を求めます。
$p$に関しては表面の各位置でベクトルの向きが変わってしまうため、$x$軸、$y$軸、$z$軸方向に分解して積分計算を行います。
圧力を$x, y, z$軸の各方向に分解すると、
$$
\left\{
\begin{split}
&x:\, -p\sin \theta\cos\varphi \EE
&y:\, -p\sin \theta\sin\varphi \EE
&z:\, -p\cos\theta
\end{split}
\right.
$$
となるので、$\diff f$も同様に各成分に分解できて、
$$
\left\{
\begin{split}
&x:\, -(p_0r^2 \,- \rho g r^3\cos\theta)\sin^2\theta\cos\varphi\diff \theta\diff \varphi \EE
&y:\, -(p_0r^2 \,- \rho g r^3\cos\theta)\sin^2\theta\sin\varphi\diff \theta\diff \varphi \EE
&z:\, -(p_0r^2 \,- \rho g r^3\cos\theta)\sin\theta\cos\theta\diff \theta\diff \varphi
\end{split}
\right. \tag{2}
$$
となります。
それでは、積分計算を実行しましょう。
まず、$z$軸周りに一回転させる($\varphi$に関して$0$から$2\pi$まで積分する)と、各方向の力の合計は次のように計算できます。
$$
\left.
\begin{split}
&x:\, -\int_0^{2\pi}(p_0r^2 \,- \rho g r^3\cos\theta)\sin^2\theta\cos\varphi\diff \theta\diff \varphi \EE
&\qquad = 0 \EE \\
&y:\, -\int_0^{2\pi}(p_0r^2 \,- \rho g r^3\cos\theta)\sin^2\theta\sin\varphi\diff \theta\diff \varphi \EE
&\qquad = 0 \EE\\
&z:\, -\int_0^{2\pi}(p_0r^2 \,- \rho g r^3\cos\theta)\sin\theta\cos\theta\diff \theta\diff \varphi \EE
&\qquad = -(2\pi p_0r^2\sin\theta\cos\theta \,- 2\pi \rho g r^3\sin\theta\cos^2\theta) \diff \theta \EE
\end{split}
\right. \tag{3}
$$
これより、リングに働く$x, y$軸方向の力を合計すると$0$になり、$z$軸方向のみの圧力のみが残ることが分かります。
$z$軸成分のみ考えればよいことが分かったので、式(3)の$z$軸方向のみについて積分すると、
\begin{split}
F &= \int_0^{\pi}(2\pi \rho g r^3\sin\theta\cos^2\theta\,-2\pi p_0r^2\sin\theta\cos\theta ) \diff \theta \EE
&= \int_0^{\pi}2\pi \rho g r^3\sin\theta\cos^2\theta\diff \theta \,-\int_0^{\pi}2\pi p_0r^2\sin\theta\cos\theta \diff \theta \EE
&= 2\pi\rho g r^3\left[ -\ff{1}{3}\cos^3 \theta \right]_0^{\pi} \,- 2\pi p_0r^2 \left[\ff{1}{2}\sin^2\theta \right]_0^{\pi} \EE
&= \ff{4}{3}\pi r^3 \rho g \,- 0 = \ff{4}{3}\pi r^3 \rho g \EE
\therefore\, F &= \rho Vg
\end{split}
と計算できます。
球の体積は$V = \DL{\ff{4}{3}\pi r^3}$であるので、浮力は$F=\rho V g$と表せます。
計算結果より、球全体には上向きに$\rho Vg$の正味の力が働くことが分かりました。
この上向きに働く力のことを浮力と呼びます。
浮力は物体の上下での圧力差に起因して生じる力であることが分かります。
また、浮力の大きさは、流体の密度と物体が排除した流体の体積のみで決まり、物体の密度や流体中の深度に無関係であることは注目に値します。
一般の場合の形状でも、微小面積に働く力を足し合わせると、$x, y$軸方向の力が打ち消し合うため、浮力は$\rho V g$となります。
たとえば、次のような直方体に働く浮力を計算すると、側面に働く圧力は打ち消し合うため、上下の圧力差のみを考えればよく、
上面に圧力が$p$、下面には$p+\rho gh$であるので、浮力$F$は、
\begin{eqnarray}
F &=& (p + \rho g h \,- p)S \EE
&=& \rho g Sh \EE
&=& \rho V g
\end{eqnarray}
となり、球での浮力と計算結果が一致することが分かります。(直方体の体積$V$は$V=Sh$より)
流体の密度を$\rho$、重力加速度を$g$とすると、体積$V$の物体には、以下で表される大きさ$F$で上向きの浮力が働く。
\begin{split}
F=\rho Vg
\end{split}
なお、浮力の大きさは流体の密度と物体が排除した流体の体積のみで決まり、物体の密度や流体中での深度とは無関係である。
今回の浮力の計算では、積分を二回に分けて実行しましたが、今後は、積分記号を次のように連続して付けた表記法がスタンダードになっていきます。
例えば、先述の$z$軸に関する浮力の計算は次のように表記されます。
\begin{eqnarray}
-\int_{0}^{\pi}\int_{0}^{2\pi}(p_0r^2 \,- \rho g r^3\cos\theta)\sin\theta\cos\theta\,\diff \varphi\diff \theta \EE
\,
\end{eqnarray}
積分を二回連続で表したものを二重積分と呼びます。二重積分の他にも三重積分、四重積分など他重積分を考えることもできます。
なぜ船は浮かぶのか?
浮力の大きさについて求められたので、鉄の塊である船がなぜ浮かぶのかについて思考を巡らしましょう。
鉄(鋼材)の密度は約$7.85\, \RM{g/cm^3}$である一方で、海水の密度は$1.03 \, \RM{g/cm^3}$です。
鉄は海水に比べて$8$倍程度重いため、鉄の塊が海水に浮かび上がって来ることはありません。
しかし、現実に鉄で出来た船は何の問題もなく、航行しています。
片方では沈み、一方では浮いているという一見矛盾した問題も浮力という現象を理解すれば、解くことができます。
例として、体積が$V_0$で平均密度が$\rho$の物体を密度$\rho_1$の流体に浮かんでいる状況を考えましょう。
物体が流体中にある程度沈み体積$V_1$だけ沈んで静止しているとします。
すると、物体に働く浮力の大きさは$\rho_1V_1g$(赤いベクトル)となります。また、重心と同様に浮力が働く中心を考えることができ、この点のことを浮心と呼びます。
今、物体に働く力は釣り合っているため、以下の式が成り立ちます。
\begin{eqnarray}
\rho_0V_0g &=& \rho_1V_1g
\end{eqnarray}
$V_0 > V_1$のため、$\rho_0 < \rho_1$となることが分かります。
この計算より、物体を流体に浮かべたいときは、物体の平均密度を流体よりも小さくしなければならいことが分かります。
つまり、船が浮かんでいられる理由は、船全体の平均密度が海水よりも小さいからであることが分かりました。
船が転覆しないためには
船と浮力の関係についてより深く考察していきましょう。
船が静止しているとき、水面に対して垂直で、重心を通る線上に浮力の中心(浮心)が来ます。(左図参照)
船に働く重力と浮力の大きさは一致しており、かつ向きは逆向きです。
以上より、力が釣り合い、モーメントも釣り合うため船は静止した状態を保ちます。
では、風や波により船体が傾いた場合に関しての船の安定性について考えてみましょう。
例えば、波や風により船が左側に傾いたとき、それに伴い浮心も移動します。(右図参照)
さて、浮心が重心よりも左側に移動した場合は、船体を右側に回転させるモーメントが働くため、船体は元の位置に戻っていきます。
このように船体を元に戻す力のことを復原力と呼びます。
メタセンタ
静止状態での船の重心と浮心を結ぶ線(軸線)は船体の傾きにより傾いてきます。
一方、船の傾きとともに浮心も移動するので、浮心を通り水面に対して垂直な線は追従して移動していきます。
この線と軸線が交わる点をメタセンタと呼び、メタセンタの位置が船の安定性や復原力の大きさを決めるます。
船の設計においては、メタセンタの位置をどこにするかが重要な設計要素になります。
トップヘビー
先ほど議論したように、メタセンタが重心より上にある場合は船体は元の位置に戻ります。
一方、メタセンタが重心よりも下に来る場合は、船体の傾くと、船体の傾きをより大きくするような方向にモーメントが働くため、船は最終的に転覆してしまいます。
このように、メタセンタと重心の位置関係により船の安定性が決まるため、メタセンタの位置は慎重に決めなければなりません。
メタセンタが重心より上:復原力が働き船は安定
メタセンタが重心より下:復原力が働かず船は不安定
船の重心位置が高い状態をトップヘビーと呼び、トップヘビーであると船が不安定になりやすいため、設計上、トップヘビーであることは望ましくありません。
さて、重心とメタセンタとの距離をメタセンタ高さと呼びますが、メタセンタが重心より上であってもメタセンタ高さが大きくなりすぎると、復原力が大きくなりすぎ乗り心地が悪化します。
したがって、メタセンタ高さが丁度良い位置になるように調整されています。
ちなみに、バラスト水はメタセンタ高さを調整するための錘として、船体に入れられます。
空荷の状態では、タンカーはトップヘビーであるため、バラスト水を入れてメタセンタ高さを調節しています。
流体力学への招待
浮力にまつわる話として、空を飛ぶ飛行機に働く浮力についても検討しましょう。
果たして、飛行機は浮力の力で飛んでいるのでしょうか?
飛行機が浮かぶのは浮力のおかげ?
ボーイング787を例に飛行機が浮力により浮かぶのかについて検討しましょう。
787-10は全長$68.3\, \RM{m}$、胴体最大幅$5.74\, \RM{m}$です。
本来は客席や内装があるため、その重量も考慮しなければなりませんが、ここでは中身が空っぽな状態での浮力について検討しましょう。
機体を円筒と仮定し、この円筒の壁の厚みを$1.5\, \RM{mm}$、円筒の材質はジュラルミンと炭素繊維のみであるとします。
このとき、ジュラルミン(密度:$2.79\, \RM{g/cm^3}$)と炭素繊維(密度:$1.65\, \RM{g/cm^3}$)が半分ずつ使われているとすると、円筒の正味の密度は$2.22\, \RM{g/cm^3}$となります。
では、この円筒の平均密度を計算してみましょう。
円筒の内側は空気(標準状態の密度:$1.29\times10^{-3}\, \RM{g/cm^3}$)が満たされていることに注意して計算すると、平均密度$\rho_{\RM{avg.}}$は次のように計算できます。
\begin{eqnarray}
\rho_{\RM{avg.}} &=& \ff{\pi\times 5.74\times1.5\times10^{-3}\times 68.3\times 2.22\times10^3 + \pi/4\times 5.74^2\times68.3\times 1.29} {\pi\times(5.74/2)^2\times68.3} \EE
&\NEQ& 3.65\, \RM{kg/m^3} = 3.65\times10^{-3}\, \RM{g/cm^3}
\end{eqnarray}
平均密度が空気の密度よりも小さいため、浮力により飛行機が浮かぶことは無いことが分かります。
それではなぜ、飛行機は飛ぶことができるのでしょうか?
この理由を理解するためには、流体の動力学的な性質を明らかにしなければなりません。
この流体の動力学的な性質を研究する力学の分野を流体力学と呼びます。
飛行機が飛ぶ理由については、こちらで詳しく検討しています。
参考記事