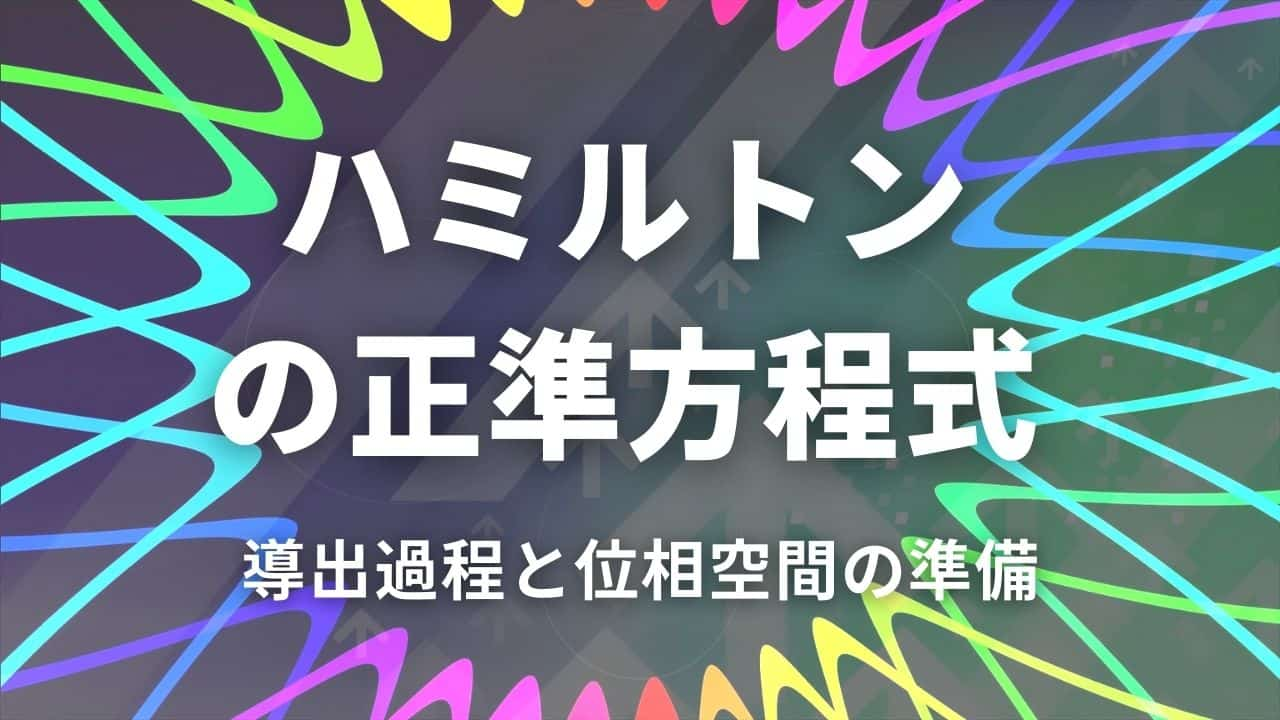今回は、解析力学のもう一つの重要な方程式である、ハミルトンの正準方程式(ハミルトンの運動方程式)の導出過程を見ていきます。
ハミルトンの正準方程式を導くモチベーションは、導出の過程で流体力学・統計力学などで使う重要な要素が垣間見えるからです。また、位相空間と呼ばれる特殊な空間での軌跡(トラジェクトリー)を計算する際にも用いられます。
今回はさらに、ハミルトンの正準方程式から運動方程式が求められることも確認します。
※ ベクトルや微分の表記についてはこちらで詳しく解説しています。
ハミルトンの正準方程式とは?
天下り的になりますが、先にハミルトンの正準方程式がどんな形をしているかを見せます。
ハミルトンの正準方程式は次のように表せます。
$H$をハミルトニアンとして、ハミルトンの正準方程式を次のように定義する
\begin{eqnarray}
\frac{\diff q_i}{\diff t} &=& \frac{\del H}{\del p_i} \EE
\frac{\diff p_i}{\diff t} &=& -\frac{\del H}{\del q_i} \\
\,
\end{eqnarray}
ここで、$q_i$は一般化座標、$p_i$は一般化運動量を表します。
なお、上付きドットは時間微分を表します。詳しくはこちらで解説しています。
さらに、ハミルトニアンはラグランジアンを$L$、系の自由度を$f$とすると次のように定義されます。
$L$をラグランジアンとして、ハミルトニアンを次のように定義する
\begin{eqnarray}
H \equiv \sum_{i=1}^f p_i\dot{q}_i \,- L \\
\,
\end{eqnarray}
後ほど具体例を使いハミルトニアンを計算します。
すると、系に働く力が保存力の場合、$H$が系の全力学的エネルギーを表すことが分かります。
それでは、ハミルトンの正準方程式の導出過程について解説していきます。
ラグランジアンとハミルトニアン
先程、天下り的にハミルトニアンの定義をしましたが、ラグランジアンとの関係を知りたくなります。
復習になりますが、ラグランジアン $L$ は、運動エネルギー $T$ とポテンシャルエネルギー $U$ を使って次のように表せました。
\begin{eqnarray}
L = T \,-\, U \\
\,
\end{eqnarray}
これからの議論のイメージをつかみ易くするため、具体的に$L$と$H$を表してみます。
ラグラジアン
二つの質点が空間を運動しているとします。
それぞれの質点の質量を$m, M$、位置と速度がそれぞれデカルト座標系にて、
$(x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2) $、 $(\dot{x}_1, \dot{y}_1 , \dot{z}_1 ), (\dot{x}_2 , \dot{y}_2 , \dot{z}_2 ) $と表せるとします。
このとき、この系のラグランジアンは次のようになります。
\begin{split}
L &= T-U \\
&= \left\{\frac{1}{2}m(\dot{x}^2_1+ \dot{y}^2_1 + \dot{z}^2_1 ) + \frac{1}{2}M(\dot{x}^2_2+ \dot{y}^2_2 + \dot{z}^2_2 ) \right\} \EE
&\qquad -\,\Big\{m_1g(x_1 + y_1 + z_1) + m_2g(x_2 + y_2 + z_2) \Big\} \\
\end{split}
ここで、座標を一般化して$x_1, y_1, z_1,\,\, x_2, y_2, z_2$を順に$x_1, x_2, \cdots, x_6$などとして、さらに、質量を$m_1, m_2, \cdots, m_6$と名前を付け替えるとこの式が、
\begin{eqnarray}
L &=& \frac{1}{2}\sum_{i=1}^6 m_i \dot{x}_i^2- \sum_{i=1}^6m_igx_i
\end{eqnarray}
と簡単かつ汎用的な形にできます。
このような形にすることで、$L$ が$x_1, x_2, \cdots, x_6,\, \dot{x}_1, \dot{x}_2, \cdots, \dot{x}_6$の関数と見なせることに気づきます。
さらに、集合の記法を使うと$\{x_i\} = (x_1, x_2, \cdots, x_6),\,\{\dot{x}_i\} = (\dot{x}_1, \dot{x}_2, \cdots, \dot{x}_6) $と簡略化できて、$L$は次のように整理できます。
$$ L = L(\{x_i\}, \{\dot{x}_i\}) $$
※質量は定数のため省略します。
次に、ハミルトニアンを具体的な形で表しましょう。
ハミルトニアンとは?
(一般化)運動量 $p_i$は $L$ を使って、$\displaystyle\frac{\del L}{\del \dot{x}_i}$の関係があります。(→ラグランジアンと運動量の関係)
したがって、
\begin{eqnarray}
p_i &=& \frac{\del L}{\del \dot{x}_i} = m_i\dot{x}_i
\end{eqnarray}
とできて、これをハミルトニアンの定義式に代入すると、
\begin{eqnarray}
H &=& \sum_{i=1}^6 p_i\dot{q}_i- L \EE
&=& \sum_{i=1}^6 (m_i\dot{x}_i) \dot{x}_i \,-\, \frac{1}{2}\sum_{i=1}^6 m_i \dot{x}_i^2 + \sum_{i=1}^6m_igx_i \EE
&=& \frac{1}{2}\sum_{i=1}^6 m_i \dot{x}_i^2 + \sum_{i=1}^6m_igx_i \EE
&=& T+U
\end{eqnarray}
となり、
ハミルトニアンが系の全力学的エネルギー($T+U$)を表すことが分かります。
また、ハミルトニアン$H$も速度と位置の関数であるため、ラグランジアンと同様に次のように表せます。
$$ H=H( \{x_i\}, \{\dot{x}_i\} ) $$
これより、一般化座標と一般化速度を用いてハミルトニアンは
$$ H=H( \{q_i\}, \{\dot{q}_i\} ) $$
と表示できます。
ハミルトンの正準方程式の導出
ラグランジアンとハミルトニアンが時間の影響を受けず、位置と速度のみで表されるとしましょう。
すなわち、系に働く外力が保存力のみであるという条件を課します。(つまり、 $L(\{q_i\}, \{\dot{q}_i\}, t)$や$H(\{q_i\}, \{p_i\}, t)$ ではなく、$L(\{q_i\}, \{\dot{q}_i\})$や$H(\{q_i\}, \{p_i\})$と表されるということです。)
さて、オイラー・ラグランジュ方程式は次のように表されました。
$$ \frac{\diff }{\diff t}\left(\frac{\del L}{\del \dot{q}_i} \right) \,-\, \frac{\del L}{\del q_i} = 0 $$
※ 詳しい導出過程はこちらで解説しています。
ここで、オイラー・ラグランジュ方程式に一般化運動量の式を使うと、
\begin{eqnarray}
\frac{\diff }{\diff t}\left(\frac{\del L}{\del \dot{q}_i} \right) \,-\, \frac{\del L}{\del q_i} &=& 0 \EE
\frac{\diff p_i}{\diff t} \,-\, \frac{\del L}{\del q_i} &=& 0\EE
\therefore \frac{\del L}{\del q_i} = \frac{\diff p_i}{\diff t} &=& \dot{p}_i \tag{1}
\end{eqnarray}
となります。
次にラグランジアン$L(\{q_i\}, \{\dot{q}_i\})$の全微分$\diff L$を考えると次のようになります。
\begin{eqnarray}
\diff L &=& \sum_i \left( \frac{\del L}{\del q_i}\diff q_i + \frac{\del L}{\del \dot{q}_i}\diff \dot{q}_i \right) \tag{2} \\
\end{eqnarray}
式(2)に一般化運動量と式(1)の結果を適用すると、
\begin{eqnarray}
\diff L &=& \sum_i \left( \dot{p}_i \diff q_i + p_i \diff \dot{q}_i \right) \tag{3} \\
\end{eqnarray}
整理できます。
そして、$\diff (p_i \dot{q}_i) = \dot{q}_i \diff p_i + p_i \diff \dot{q}_i$であることを利用すると、
次のように移項して式(3)を変形できます。
$$
\begin{split}
&\diff L = \sum_i \left( \dot{p}_i \diff q_i + p_i \diff \dot{q}_i \right) \EE
&\quad = \sum_i \left\{ \dot{p}_i \diff q_i + (\diff (p_i \dot{q}_i) – \dot{q}_i \diff p_i ) \right\} \EE
\therefore\,\,\,&\diff\left( \sum_i p_i\dot{q}_i-L \right) = \sum_i (- \dot{p}_i\diff q_i + \sum_i \dot{q}_i \diff p_i)
\end{split}
\tag{4}
$$
左辺に見覚えのある形が出てきました。
ここで、ハミルトニアンが $H = \sum_i p_i\dot{q}_i-L $ で表せることを使うと式(4)は、
\begin{eqnarray}
\diff H &=& \sum_i (-\dot{p}_i\diff q_i + \sum_i \dot{q}_i \diff p_i) \tag{5}
\end{eqnarray}
とできます。
さらに、$H(\{q_i\}, \{p_i\})$であるので全微分$\diff H$を考えると、
\begin{eqnarray}
\diff H &=& \sum_i \left( \frac{\del H}{\del q_i}\diff q_i + \frac{\del H}{\del p_i}\diff p_i \right) \tag{6}
\end{eqnarray}
となり、式(6)と式(5)を比較すると、ハミルトンの正準方程式が導出できます。
$H$をハミルトニアンとして、ハミルトンの正準方程式は次のように表せる
\begin{eqnarray}
\frac{\diff q_i}{\diff t} &=& \frac{\del H}{\del p_i} \EE
\frac{\diff p_i}{\diff t} &=& -\frac{\del H}{\del q_i} \\
\,
\end{eqnarray}
これにて、ハミルトンの正準方程式の導出が完了しました。
次は、ハミルトンの正準方程式より運動方程式が本当に出てくるのかを検証しましょう。
ハミルトンの正準方程式と運動方程式
単振り子を例にして、ハミルトンの正準方程式から、運動方程式が導かれることを確認します。
単振り子が下の図のような状態で運動しているとします。
まず、ラグランジアン$L$は、
\begin{eqnarray}
L &=& T -\, U \\
&=& \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 \,-\, mgl(1-\cos\theta)
\end{eqnarray}
であり、一般化運動量 $p_{\theta}$ は次のようになります。
$\dot{\theta}$の微分では、$\theta$を定数として扱うことに注意してください。
\begin{eqnarray}
p_{\theta} &=& \frac{\del L}{\del \dot{\theta}} \EE
&=& ml^2\theta
\end{eqnarray}
$\DL{\dot{\theta} = \frac{p_{\theta}}{ml^2}}$となるので、ハミルトニアン$H$は、
\begin{eqnarray}
H &=& p_{\theta} \cdot \dot{\theta} \,-\, L \\
&=& p_{\theta} \cdot \frac{p_{\theta}}{ml^2} \,-\, \left\{ \frac{p_{\theta}^2}{2ml^2}\, -\, mgl(1-\cos\theta) \right\} \\
&=& \frac{p_{\theta}^2}{2ml^2} + mgl(1-\cos\theta)
\end{eqnarray}
となります。
これをハミルトンの正準方程式に代入すると、
\begin{eqnarray}
\frac{\diff \theta}{\diff t} &=& \frac{\del H}{\del p_{\theta}} = \frac{p_{\theta}}{ml^2} \tag{7} \EE
\frac{\diff p_{\theta}}{\diff t} &=& – \frac{\del H}{\del \theta} = -mgl\sin\theta \tag{8}
\end{eqnarray}
できて、式(7)をさらに時間微分して、次のような関係式が得られて、
\begin{eqnarray}
\ddot{\theta} &=& \frac{1}{ml^2} \frac{\diff p_{\theta}}{\diff t} \EE
\frac{\diff p_{\theta}}{\diff t} &=& ml^2\ddot{\theta}
\end{eqnarray}
となります。
これを式(8)に代入すると、
\begin{eqnarray}
ml^2\ddot{\theta} = -mgl\sin\theta
\end{eqnarray}
となり、運動方程式がきちんと導かれました。
この後は$\theta$が微小であることを利用して式を近似して解いていきますが、今回この過程は割愛します。
※ 単振り子の詳しい解法についてはこちらで解説しています。
このように、ハミルトンの正準方程式を利用して、きちんと運動方程式が導けることが分かりました。
ハミルトンの正準方程式などという珍妙な式がどんな場面で活躍するのかは、位相空間に関する記事で詳しく解説していきます。
位相空間を考えることで三体問題に解析解がないことをより直観的に理解できるようになります。